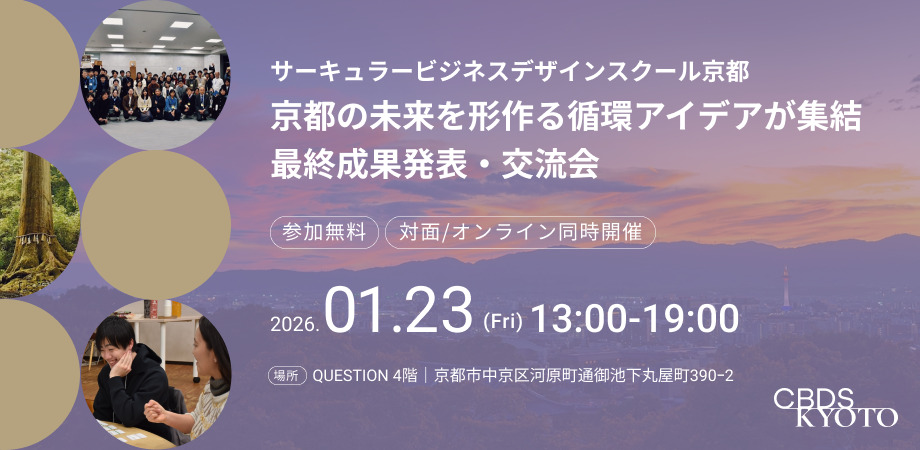3月、常夏と言われるハワイでも、少し肌寒いなと感じる日々がある季節です。特にこの数週間は、北太平洋に大きな高気圧が発達して、冷たい北風が吹きつけています。寒いと言っても長袖を一枚羽織れば何とかなるほどですが、誰かと会うとついつい、「今日も寒いねえ」が挨拶になっている毎日です。
気温はそれほど下がらないハワイにも、「冬」というのは確かにあって、それを感じさせてくれるのが、遥か北、アラスカあたりから越冬のためにやってくる、ザトウクジラや渡り鳥たちの存在です。毎年11月頃になると、彼らがいつ到着するかなと心待ちに過ごします。
今年もたくさんのザトウクジラや渡り鳥たちに出会いました。数千キロも離れた北の地から、彼らは一体どうやってハワイを見出しているのでしょう。大海原を越えて遥々やってくる彼らの姿を見るたびに、この世界はまだまだたくさんの不思議に満ちていることを思い出します。

海を見るたびに、クジラの姿を探す毎日
ハワイの神話と伝統作物
つぎつぎ生える野菜と聞いて、ハワイで真っ先に思い浮かぶのは、Kalo(カロ)と呼ばれるタロイモです。カロはハワイの伝統食の主食で、一口にカロと言ってもその色や風味、香りなどが様々で、18世紀の終わりに西洋人がハワイを訪れる前には、300種類以上のカロが栽培されていたそう。
このカロ、収穫のときにイモの部分を切り取り、残った茎を畑に差すと、そこに再び新たなカロがつきます。これを何度も繰り返すことができ、まさに無限に収穫することができるんです。
ハワイに語り継がれる神話では、この世に初めて登場したカロは、天を司る神ワケアとホオホクカラニの第一子から生まれたといわれています。第一子は生まれてすぐに命を落とし、家のそばに埋葬されました。するとそこからカロが芽吹き、ハーロアナカラウカパリリと名付けられました。次に生まれた二番目の子供は、最初の子供の名前の一部をとってハーロアと名付けられ、最初のハワイアンになりました。
カロとハワイの人々は、神話上、兄弟なんです。大地に育まれてカロが生まれ、ハワイの人々の生命を支える。まさに自然も人もひとつだったんだなあと思います。
カロは蒸したものをすり潰してペースト状にし、「ポイ」と呼ばれる形にして食べるのが一般的です。ただ蒸しただけだと、すぐに傷んでしまうのが、ポイにすると常温で長く置いておけるようになります。少しずつ発酵して独特の酸味が出てくるのですが、その酸味がたまらないという人も多い。カロは一気にたくさん採れるので、ポイにすることで、多くの人と分かち合うことができます。まさにシェアの知恵ですね。

わが家で収穫したカロ。ハート型の葉が可愛いい
シェアから生まれる大いなる流れ
春、ハワイでは年に一度のカヌーフェスティバルが開かれます。
ポリネシアの伝統航海文化を祝うこの祭典、1975年にホクレア(ハワイを代表する伝統航海カヌー。詳しくは往復書簡2に)が進水式を行なった、クアロアと呼ばれる美しいビーチに、ハワイで活躍する数々の航海カヌーが集う、晴れやかな一日です。
ポリネシアの伝統航海は、1970年代にホクレアが誕生するまで、数百年の間、途絶えてしまっていました。ホクレアの建造に関わったメンバーは、伝承や考古学の研究を元に、カヌーそのものを復元することはできたのですが、星や波など自然のサインを読む伝統的な手法を使って航海ができる人を見つけることはできませんでした。
そこに手を差し伸べたのが、ミクロネシアの航海術師、マウ・ピアイルグです。マウはハワイの人々の伝統復興への思いを知り、それまで門外不出とされてきた伝統航海術をハワイの人々と分かち合う、という大きな決断をしました。
マウの導きのもと、ホクレアは1976年にハワイからタヒチに向けた4千キロの航海を、コンパスなど計器を一切使うことなく成功させます。その成功はポリネシアの人々が、深い部分からの誇りを取り戻すきっかけになり、ポリネシア中で伝統文化の復興が始まりました。
私自身も含め、カヌーフェスティバルを運営するメンバーの多くが、マウの教え子です。私たちは師匠であるマウを敬愛を込めて「Papa Mau」と呼んでいます。マウは私たちにとって父のような存在。彼の分かち合いから生まれた流れの中で、私たちもまた次の世代に多くを分かち合っていきたい。皆がそんな思いのもとに活動しています。
ハワイでも数多くの航海カヌーが誕生し、各地で、海と人のつながりを取り戻す素晴らしい活動が展開されています。

ビーチに一堂に集った航海カヌーと、その航海カヌーを堂々と操る若い世代たち。そのまわりできゃっきゃっとはしゃぐ、たくさんの子どもたち。この豊かで美しい光景が、一人の師が、50年ほど前に、彼の知恵と経験をシェアしたことをきっかけに生まれたと思うと、胸がいっぱいになります。
シェアする、分かち合うということには、その行為そのものに、大きなエネルギーがあるような気がします。分かち合いがひとつの流れとなり、そこにたくさんの支流が集まって、大きな流れが生まれる。そしてその大いなる流れが、数え切れない人々へと恵みを運ぶ。そんなイメージを抱いています。

ホクレアに描かれたマウ
自然と人と私たちの生命の巡り
今年のはじめ、マウイ島のラハイナまで航海しました。2023年の8月、乾いた大地で起きた火事が強風に煽られて瞬く間に広がり、町のほとんどが焼け野原になるという大災害が起きたラハイナ。災害直後は、航海カヌーで救援物資を運んだり、基金を集めたり、なんとかできることに取り組みましたが、被害の甚大さを前に、ただただ無力を突きつけられる毎日でした。
かつてハワイ王国の首都であったラハイナは、もともと緑溢れる場所だったといいます。いくつもの沢が流れ、地下水も豊かで、海辺には湿地帯もありました。タロの畑が広がり、そのまわりには、ウル(パンの木)やククイ、ニウ、ハラなど、たくさんの木々が植えられ、灼熱の太陽から大地を守っていました。ラハイナには「ウルの木の木陰」という別名もあったほどです。
19世紀に入ると、大規模なプランテーションが始まり、タロの畑を潰し、木々を切り倒して、サトウキビ畑が作られました。サトウキビ産業が衰退すると、畑は放置され、外来種の草が辺りを覆い尽くしはじめます。沢の水は枯れ、大地はカラカラに乾いていました。
異常なほどに乾いた大地に、火は瞬く間に広がりました。誰も止めることができなかった歪んだ土地利用。西欧化に翻弄された150年の中で失われた、大地とのつながり。ラハイナの大災害は、自然と人の関わりのあり方が、いのちに直結することを私たちに突きつけます。

航海の日、マウイ島の沖合いから朝日に照らされるラハイナに向けて舵を切ると、どこからともなく何頭ものザトウクジラたちがカヌーの周りに集まり、大きく潮を吹きながら、ゆったりと伴走しはじめました。それはまるで夢の中のような出来事で、私たちはみな息を飲み、その光景を見つめていました。
災害から半年以上たった今も、復旧への道のりはまだまだ先が見えません。おそらくこれから何年もかけて取り組んでいかなければならないラハイナをどのように復興していくのか。限りある水をどう使っていくのか。失われた循環をどう取り戻すか。いのちを優先する暮らしをどう形にしていくのか。ラハイナの未来に向けた問いかけは、ハワイ全体、そして地球全体への問いかけのように思えてなりません。
photo: 著者(1-6枚目)
【関連ページ】【海をわたる往復書簡 ハワイー高知#3】自然の恵みをシェアすること
【関連ページ】海をわたる往復書簡 ハワイー高知
【関連ページ】【連載】服部雄一郎・麻子さんに聞くゼロウェイストな暮らしのアイデア
【関連ページ】【連載】服部麻子さん「あるものでごはん」
内野加奈子
最新記事 by 内野加奈子 (全て見る)
- 【海を渡る往復書簡 ハワイー高知 #12】海を越えて響きあう。「今ここ」を生きる - 2025年2月24日
- 【海を渡る往復書簡 ハワイー高知 #10】国境も時空も超えてゆく旅 - 2024年11月29日
- 【海をわたる往復書簡 ハワイー高知 #8】身体の感覚を解放して「変化の波」と上手く付き合う - 2024年6月15日