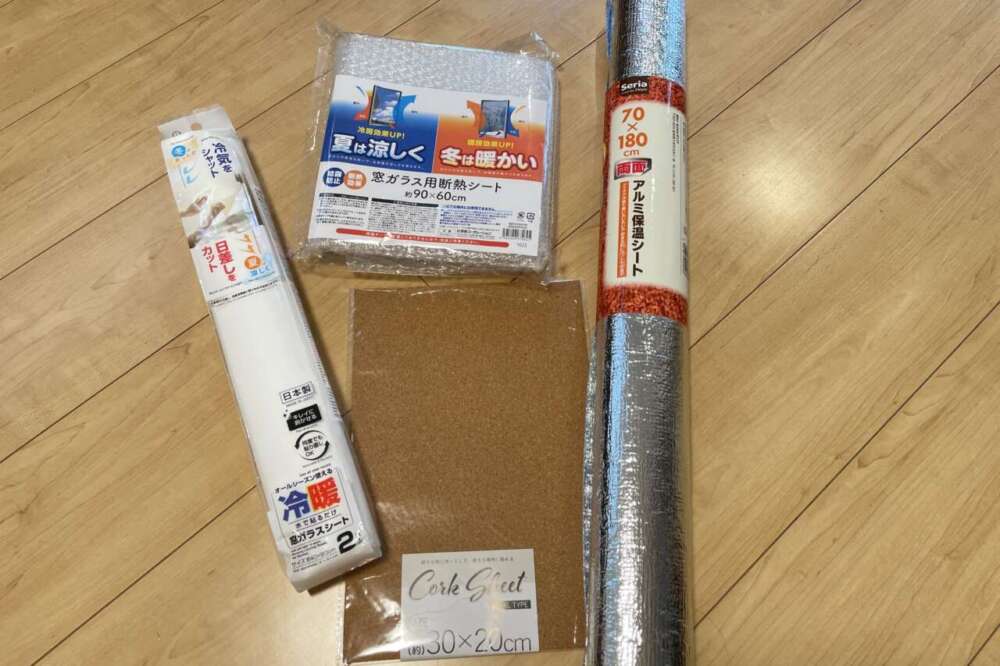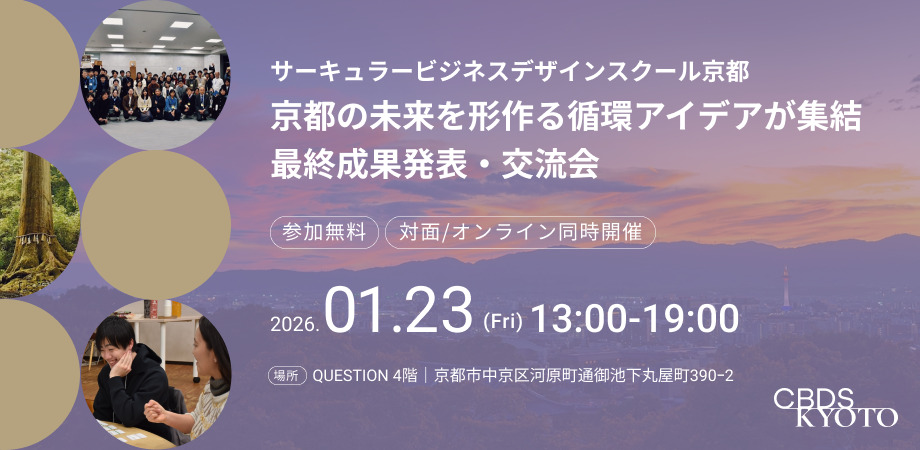春から夏に向かうこの季節、山の上での茶摘みや畑の収穫など、前回の麻子の書簡
から、高知での日々を彩る溢れんばかりの自然の恵みにうっとりします。日本は、四季それぞれの恵みが驚くほど豊かだということを、離れているとますます感じます。
ハワイにいてこの時期、恋しくなるのが、青梅のほのかな香りです。めったに手に入らないのですが、先日、日系食品店に並んでいるのを見つけて、喜び勇んでで帰ってきました。ほんのちょっぴりだけれど、数年ぶりの「梅仕事」。一粒ずつ丁寧に洗って、梅シロップを漬けました。

自身の体に起こる「変化の波」
それなりに生きてきて、もう長い付き合いになる自分の身体や心のコントールをそろそろマスターできていてもいいのでは?と思いますが、なかなかそうもいかず。
年齢を重ねるなかで、自分の身体ばかりでなく、周りの環境や求められる役割なども変化し続けているのだから、それも当然のことかもしれませんが、気をつけていても、ストレスが溜まったり、体調がいまひとつだったりはよくあることです。
これは誰にでも起こりうることだと思うのですが、それでもなかなかしんどい。
そんな時、私が心がけているのは、気分の落ち込みは、身体の問題、と割り切ることです。はじまりが頭だったとしても、すでに身体の問題へと移行している、と見込んで、淡々と身体側から対処します。
まずひたすら休む。無理に動こうとしない。
大事なのは、休む自分を責めないこと。早く元気になって、いろいろやらないと、という、そもそも自分をストレスに追い込んだ在り方への処方箋です。
次に栄養不足を疑う。
イライラ、ぐるぐる思考などで、大量のストレス物質が出て、身体が普段より栄養を使っていると仮定します。もしくは、もともと足りていなかったので、ストレスへの耐性が低くなっていた可能性も。特に鉄分とタンパク質は、意識して摂ると、身体がすっきりしてきます。

南国ならではの恵みといえば、バナナやマンゴー、パパイヤやアボカド。
夏に向けて、たわわに実る季節です
一番苦手だけれど、大切なのは、
睡眠パターンに気をつけること。
睡眠が、体調、精神面に大きく影響を与えることを頭では理解しているつもりでも、調子の悪いときにかぎってなかなか寝れなかったり、すっきり起きれなかったり。自力で戻すのもなかなかむずかしい。
そんな時は、朝起きたらまず、太陽の光を浴びます。目を瞑って、太陽の光に目を当てる。
「体内時計さん、わかります?いま、朝なんですよ」とひたすら身体にアプローチ。
ポイントは “他力”。
自分の力でなんとかしようとしない、ということです。
ひたすら休んで、栄養あるもの食べて、太陽の光を浴びる。
やる気が出ないことを、否定も肯定もしない。
気分が落ち込むことも、否定も肯定もしない。
心の声に、そうなんだね、そうなんだね、と耳を傾けながらも、
アプローチは身体から。
するといつの間にか、自然と回復しています。
気分の落ち込みは、もしかしたら、ストレス過多に対する、からだの防御反応なのかもしれませんね。だからこそ、気づいたら、身体面から淡々とケアするようにしています。

息を呑むような朝焼けや夕焼け空に力をもらうことも
身体の感覚を研ぎ澄ました先にある、生命のスイッチ
私はそれほど体力のある方ではないのですが、海の上にいると、不思議と疲れが出ません。
大海原を航海するカヌーの上は、特殊な生活空間です。常に揺れているし、強烈な太陽や、風や雨にも晒されます。プライベートな空間もほぼなく、かじ取りなどの役割があるので、睡眠パターンも不規則。
ある意味、過酷な環境ともいえるのに疲れが出ないのは自分でも不思議です。でも、もしかしたらそれは、海で「生命のスイッチ」が入るからなのでは?と思っています。
私たちは日々、屋根のある家に暮らし、雨や風から身を守る必要もありません。水や食べものを得るために、毎日水汲みに行ったり、森に出かけたりする必要もありません。それでも私たちには、全身の感覚を研ぎ澄ませるときにこそみなぎる、生き生きとした生命力のようなものがあるのでは、と思うんです。
普段の暮らしで、そんな生命のスイッチを入れてくれるのは何だろう?と、探求している今日この頃です。

アラスカの海で、現地の皆さんに勧められた、氷河の溶けた水に飛び込むアイスウォータースイム。痺れるほどの冷たさでしたが、上がった後は身体ポカポカ、頭はすっきり。まさに生命のスイッチでした
波の下に広がる海
このところはずっと、変化の波、というテーマを思い浮かべながら、海を眺めていました。
穏やかな海がどこまでも続く日、大きな波が絶え間ない日、風で白波が立つ日。毎日、一度として同じ海はありません。
波という漢字は、水を表す「氵」に「皮」と書きますが、まさに波は海の表面のうすい皮のようなもの。私たちの目に映る表層が、どんな大波で荒れていても、その下にはいつも、ただただ静かで深遠な海がじっと存在しています。

変化の波が時に苦しくなるのは、もしかすると、波の中に入り込みすぎているからかもしれません。私たち一人一人の中には、どんな変化も、ものともしない大いなる生命があり、波の下にいつも存在してくれている。
「楽しむ」とは、単に面白いとか心地よいということだけではなく、「その感覚を十分に味わう」ことも含まれているはず。 (往復書簡Vol.7から引用)
麻子が書いてくれた、この「その感覚を十分に味わう」というのは、私たち一人一人が、自身の“生命”へとつながる鍵を握っている気がします。頭から少し離れて、身体の感覚に目を向け、十分に味わう。それが、波の下に広がる生命の海への橋渡しをしてくれるように感じるのです。
パシフィックの祭典「太平洋芸術文化祭」
ハワイは今、太平洋芸術文化祭(FestPAC)の開催に沸いています。

クック諸島からハワイへ向けて航海した航海カヌー「Marumaru」
祭典に合わせ、クック諸島の航海カヌーが、23日間の大航海をへてハワイに到着しました。大海原で彼らは、一体どんな景色を見てきたのでしょうか。太平洋のあちこちから、新たな波が届きつつあるのを感じています。

クック諸島から到着したクルーと出迎えた家族のみなさん。皆、満面の笑み。
photo: 著者(1-8枚目)
【関連ページ】【海をわたる往復書簡 ハワイー高知 #7】変化の波とのつきあい方
【関連ページ】海をわたる往復書簡 ハワイー高知
【関連ページ】【連載】服部雄一郎・麻子さんに聞くゼロウェイストな暮らしのアイデア
【関連ページ】【連載】服部麻子さん「あるものでごはん」
内野加奈子
最新記事 by 内野加奈子 (全て見る)
- 【海を渡る往復書簡 ハワイー高知 #12】海を越えて響きあう。「今ここ」を生きる - 2025年2月24日
- 【海を渡る往復書簡 ハワイー高知 #10】国境も時空も超えてゆく旅 - 2024年11月29日
- 【海をわたる往復書簡 ハワイー高知 #8】身体の感覚を解放して「変化の波」と上手く付き合う - 2024年6月15日